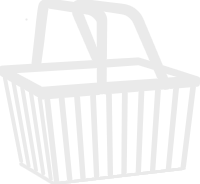History
京黒紋付染(きょうくろもんつきぞめ)の歴史
京都に都が制定され、すでに1200年以上。
この都には、四季折々の美しい自然の変化があります。
周囲の山々の頂きには、春夏秋冬それぞれの色彩に染まり、地から湧き出る清い水は、南北に流れる何本もの清流となります。
そうした自然環境が、色彩感覚の富んだ人々を育んできました。
その色彩感覚と、京都の自然環境は染めの世界にも深く影響を与えています。
特に欠かすことのできない京都の水は、染め色にも特別なニュアンスを与え、伝統ある京染めを生み育ててきたのです。

京紋付黒染のはじまり
京染めのなかでも、京黒紋付染の歴史は長く、平安時代にまで遡ります。
その頃は墨を用いる黒染めが主流でしたが、やはり黒の色は浅く、その後も試行錯誤が重ねられてきました。
京黒紋付染めの確立

現代につながる京黒染め(京黒紋付染め)は、17世紀初頭に確立されました。
江戸時代、武士の間で、檳榔子染(びんろうじぞめ)による黒紋付が愛用されたといいます。檳榔子とは、檳榔という植物の種子のこと。マレーシア原産のこのヤシ科の植物は、日本へは天平勝宝8年(756年)に渡来し、薬用に用いられましたが、この頃、染料としても利用されるようになりました。
武士に好まれたのは、檳榔子の染料に含まれるタンニンが刀を通さないほど絹地を強くするといわれるためで、護身用として好まれたのです。
その後、ヨーロッパの染色技術や化学染料の導入によって京黒紋付染めの黒はいっそう磨かれ、藍下(あいした)、紅下(べにした)や三度黒(さんどぐろ)などの現代につながる技法が確立されました。
社会風俗と京黒紋付染
明治以降に喪服として浸透
先にも述べたように、礼服として定められた黒紋付ですが、特に不祝儀の際の正式礼装(喪服)のイメージが強いかもしれません。
しかし、その歴史は意外に新しいのです。
そもそも、明治32年(1899)、永照皇太后(明治天皇御母)が亡くなられた際に、当時の宮内省(現宮内庁)が「喪服は白衿紋付(しろえりもんつき)」と告示したように、喪服は白とされていました。

ところが、文明開花の時代、欧米では葬儀に黒い服を用い、また洋装では黒のモーニングなどのフォーマルを着始めた時代でした。そうした中でも、和装では白喪服を着用していましたが、次第に西洋に倣い、上流社会の人々は黒の喪服を着用するようになったようです。
大正初頭には宮中参内の喪服として「きものは黒無地紋付、帯は黒の丸帯、帯留(帯〆)は丸ぐけの白※、帯揚げは白※、足袋は白、はきものは黒草履」と定められ、黒が主流となってゆきます。とはいえ、あくまでも当時の上流婦人たちの風習であり、広く一般に定着したのは昭和に入ってからと言われています。
そもそも、男性の正式礼装である紋付羽織袴は元来、江戸時代の武家の日常着でした。後に上層町人が式服として着用するようになり、祝儀・不祝儀両用の礼服として、現代に引き継がれています。
女性の黒紋付も、礼節を表す正礼装であることから葬儀にかぎらず結婚式でも着用できます。
喪服の制度は奈良時代から
さて、喪服の話が出たところで、少しその歴史を振り返ってみます。
死者を悼み、そのけがれを忌むために喪服を着る習慣は、古くから世界各地で行われていました。
古代の日本でも、藤葛などの繊維を織った「ふじごろも」と呼ばれる粗末な服が用いられていたようです。
また、素服と書いて「あさのみそ」「いろ」などと呼んだという記録も残っています。
これが正式の喪服として定められたのが奈良時代のこと。
「養老令」によれば、天皇の着るべき喪服が、死者の身分に応じて定められており、
錫紵(しゃくじょ)と呼ばれる浅黒色の喪服も含まれていました。

しかし、一般の喪服はまだまだ、「いろ」「いろぎ」などと呼ばれる生地のままの麻服が主流。
「いろなし」の略語あるいは「白」の反語が、その語源と考えられています。
黒の深さで区別した平安時代

この時代の宮中では、「素服」という言葉が黒い袍(わたいれ)を意味するほどに、黒い喪服が普及します。ひとつには椽染(つるばみ)をはじめとする黒染の技術が発達したからでしょうか。
ただ、同じ黒といっても死者との縁の遠近や服喪の時期によって使い分けがあり、死者との縁が近いほど黒い服(重服)を、遠いほど鈍色(にびいろ)(薄墨)の服(軽服)を用いていました。「中将の君、鈍色の直衣、指貫うすらかに衣がへして」…妹である葵の上の法事の後、その夫である光源氏を見舞った三位中将の装いです。