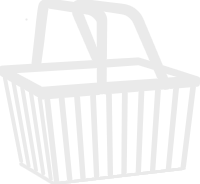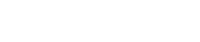京の技を紡ぐ『黒染め』で
愛着あるお洋服が生まれ変わる

京の技を紡ぐ『黒染め』で
愛着あるお洋服が生まれ変わる


Kurozome
京黒染めについて
京都に都が置かれて、およそ千二百年。
往時のまま、山々は春夏秋冬の色を醸し出し、
湧き出づる清き水が、私たちを潤します。
その都で「京黒染め」は育まれました。
歴史を重ね、深みを醸す「京の黒」
私たち馬場染工業では、
「お洋服の黒染め替え」など 現代に合わせた
ものづくりで、京の技を受け継ぎます
伝統を受け継ぐ
京黒染めを
今に取り入れる
京の黒染屋『馬場染工業』
明治3(1870)年創業。京黒紋付染の「馬場染工業」の紹介動画です。京黒染の老舗としてのこれまでとこれからをお届けします。
Service
お客様向けのサービス
黒染め替え
お洋服や小物など
ご愛用の衣類が
黒で生まれ変わります
Somekae Gallery
京都家紋体験工房
伝統の家紋や武将紋
現代的な花個紋で
家紋入れを体験
京黒紋付染のお誂え
他では出せない「黒より黒い黒」
私たちオリジナルの「秀明黒」で
長くご愛用頂ける1着を
家紋グッズのオーダー制作
伝統から現代的な衣装まで
家紋を用いたオリジナルの
グッズ制作を承ります
Our Story
『京の黒染屋』のおはなし
馬場染工業株式会社
〒604-8242 京都府京都市中京区
西洞院通三条下ル柳水町75
tel.075-221-4759
(受付時間 9 時~ 17 時)